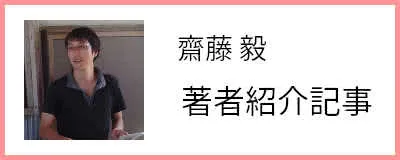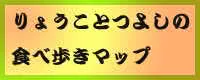今回は渋くて苦いカカオ豆はどうして利用されるようになったのか?の続きの内容を踏まえて、チョコレートの製造について触れ始めたい。
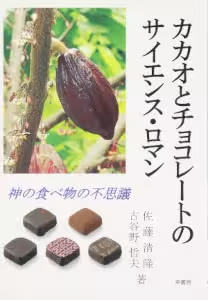
幸書房から出版されている佐藤清隆 古谷野哲夫著 カカオとチョコレートのサイエンス・ロマン 神の食べ物の不思議を読み進めると、カカオ豆からチョコレートになるまでの話で、カカオ豆の原産地ではチョコレートを作る事は不可能※で、大航海時代以降にヨーロッパに持ち込まれる事で、チョコレートへ変化していく可能性を得たが、それでもカカオ豆の化学的な要因でチョコレートにすることはできず。
※ 現在は科学技術の発展で原産地でチョコレートを作る事は不可能ではなくなった
ヨーロッパでの社会的情勢により、カカオ豆の需要が減った事と重なってカカオ豆の利用方法の開発の試行錯誤の結果、チョコレートが誕生するという熱い展開があるそうだ。
上記の本では、更にミルクチョコレートの開発についても記載されているが、それもまた化学的な話題で熱い展開となっている。
何故原産地でカカオ豆からチョコレートの製造が不可能であったのか?
それを理解する為には、カカオに豊富に含まれる脂質について触れていく必要がある。

話は少し脱線するが、カカオ豆の原産地では、どのようにしてカカオ豆を利用していたか?というと、コーヒーのように飲料として利用されていたそうだ。
であれば、現代社会の日本においてカカオ豆もコーヒーのように利用されていてもおかしくないがそうではない。
カカオ豆にはコーヒー豆と大きく異なる点があるはずで、その特徴こそが後のチョコレートへと繋がっていくはず。
カカオ豆の大きな特徴というのが、カカオ豆の成分の半分が脂質になっている。
この脂質の融点が低いそうで、この融点の低さがチョコレートのサイエンスへと導いていく。
融点というのは、物質が固体から液体に変化する際の温度を指し、カカオ脂質は25℃までは油脂中の80%以上が固体だが、25℃を超えると急速に溶け始め、32~33℃付近でほぼ完全に溶けて液体になるそうだ。
カカオ豆が自生している地域は熱帯雨林で、カカオ脂質の融点を超えている事が多く常温で液体であるため飲料として利用できるが、ヨーロッパでは気温が低く常温で個体である事が多いので、カカオ飲料としての利用は難しいそうだ。
※コーヒーの融点は200℃付近
栽培地ではカカオ豆をコーヒーのようにして飲んでいたそうなので、ヨーロッパでも温かい飲料として広まったのでは?と思うかもしれないが、コーヒーの方が利便性が良くカカオ飲料の需要は低かったそうだ。
そんな中で、カカオの脂質を話題の中心にして、ココアやチョコレートの開発の話へと続いていく。