今年も天日干しのレンゲ米を頂いた


昨年投稿した米の食味検査の結果が過去最高になったという連絡があったの記事に引き続き、今年も報告と合わせて天日干しのレンゲ米を頂いた。
今年の栽培では課題がいくつか挙がり、その内容は水田で高温対策として昼間のかけ流しをするべきか? - 京都農販日誌で投稿している。
米の食味検査の結果が過去最高になったという連絡があった


新米を頂いた。
新米を頂いた経緯は私の指導で今年の米の食味検査で結果が過去最高になったとのことで受け取って欲しいという連絡があった。
上記では栽培指導をしたことになっているが実際のところは栽培の指導はしていなくて、高槻の原生協コミュニティルームでレンゲ米栽培の観測の報告会を行いましたの記事で記載している報告会に参加した方が事例を自発的に取り入れた事で食味が向上したようだ。
上記の報告会は、自身の稲作の知見の整理の為に自発的に開催したもので、こうすれば食味が良くなるといった内容は一切していない。
報告会に参加していて食味検査の結果が上がったという報告を受けたのは今回で二件目で、整理した知見の中に品質向上の鍵となる要因があることは間違いなさそうだ。
報告会で話した内容は米の粒の大きくしたいという相談がありました - 京都農販売等の記事で記載している。
高槻の摂津峡付近でアレチウリを見かけた

河川敷にいたグリーンモンスターことマメ科のクズの上に薄い緑の葉の草が覆おうとしていた。

この葉、

このトゲトゲの果実はウリ科のアレチウリか?
大阪北部に引っ越してからはじめて見かけた。
アレチウリといえば、周辺の農地や生態系に悪影響を与える草として、発見次第速やかに除去すべき草として扱われている。
冒頭の写真では、アレチウリがクズを覆う面積が少ない為、おそらくまだここにたどり着いたばかりなのだろう。
今除去すれば広がらないのだろうけれども、クズの茂みに手を突っ込むのは嫌だな。

アレチウリは巻きひげを巧みに扱い、クズの上を覆うように展開しているので、いずれはクズを負かしてアレチウリだらけになるのだろうなと。

花にはスズメバチやアシナガバチがたくさん寄っていたので、それもたちが悪い。
関連記事
今年もシイの木の開花の時期がやってきた
天気が良いので、近所の山の方に目を向けてみると、

林冠と呼んで良いのだろうか?
山の高い位置で黄色くこんもりした箇所がある。

おそらくこれはシイの木の花だ。
今の時期はたくさんの草木が花を咲かしてくれるので、植物名を調べて勉強するのにもってこいの季節だ。
今の時期にシイの木が何処に生えているのか?を把握しておこう。
シイの木といえば、

スダジイの尾状花序の上をハナバチが歩くの記事で書いたけれども、ミツバチを含むハナバチにとって花蜜と花粉が多いボーナスのようなものだと個人的には思っていて、


ドングリにはタンニン(人体に対する毒性)が少なく、人を含む動物たちにとって素晴らしい食料となるため、好きな植物の一つだ。
シイの木は上記の理由から昨今の様々な環境問題を解決する重要な木であると個人的には捉えているのだが、シイの木は耐陰性が強く、極相種(森を形成する上で最後の方に生えてくる木)として扱われているので、道は険しく長くなるだろうなと。
関連記事
高槻米の米粉「清水っ粉」からできた米粉めんを頂いた
昨年同様、高槻の原の生協で物理性の改善 + レンゲ栽培 + 中干し無しの稲作の検討会を行いまして、その際に、
高槻の原生協コミュニティルームでレンゲ米栽培の観測の報告会を行いました



大阪産(もん)に認定されている高槻「清水っ粉」でできた米粉めんを頂いた。
試食した感想は、うどんのような歯ごたえが有りつつ、そうめんのような滑らかな舌触りで、米のような甘みがほんのり残っていて、新たな麺料理といった感じであった。
この米粉めんは100%米粉からできているとのこと。
麺のつなぎも米粉が?といった話があるが、科学の視点で深くなりそうなのでここまでにしておく。
新しいものづくりをする時に大事になるのは、製造技術の確立と出口(売る先)が必要だと言われている。
清水っ粉や今回の米粉めんは、

物理性の向上 + レンゲ栽培 + 中干しなしの稲作の新たに生じた課題
環境貢献度を高くしつつ、収量や品質を高めるような栽培技術の開発から着手し、通常の米食に加え、パンや麺といった出口も増やした。
田からはじめる総合的病害虫管理の記事でも触れたが、田は周辺の畑作に良い影響を与え、地域全体を底上げできる可能性を秘めているので、物理性の改善 + レンゲ栽培 + 中干し無しの稲作と米粉の取り組みが広がって欲しいと切に願う。
今年も観測していたレンゲ米栽培の田が無事に収穫を迎えたそうです

物理性の向上 + レンゲ栽培 + 中干しなしの稲作の新たに生じた課題までの記事で観測していた田の収穫が無事終了したという報告があったので行ってみた。

株が傾いていたので、肥料の効きすぎで株が弱体化したのでは?と不安になったが、収穫機がうまく動作しない箇所があったとのことで、株は硬く穂重があったということなのだろう。


今年は穂の形成期の気温が低かったため、中干しなしという選択で低温障害や穂いもちが助長される懸念事項があったけれども、

黒ずんだ籾から胚乳を取り出しても、懸念した内容が悪影響を与えたということはなさそうだ。
今年は中干しの意義の確認を最重要事項にした。
物理性の向上 + レンゲ栽培 + 中干しなしの稲作の新たに生じた課題の記事で触れた内容になるが、年々異常さが増してくる夏の猛暑に対して、中干しをしないというのが大きな一手になると予想していて、中干しなしと中干しありの田の比較の観測を行った。
※最低限の環境として物理性の向上 + レンゲ栽培がある。
中干し無しの田で見られた現象として、

猛暑日を経て、登熟期に差し掛かる時に葉の色が落ちなかった。
・レンゲによる土作りで肥料分が過多になってしまったことか?
・猛暑日に中干しなしで株を冷やし、葉温を高くなりすぎないようにしたことか?
・常に水があることで、川から流入した金属系の栄養が常にあったことか?
といった事が考えられるが、肥料分の過多が一番影響がありそう。
※中干しありの田は他の田同様、葉の色落ちは早い。
もう一つは、


イネの害虫だとされるカメムシやウンカ(どちらもカメムシ目)の天敵が集まった。
中干しなしの栽培方法はウンカの被害を軽減させるために有効であるという仮説があったが、昨年程ウンカの目立った被害がなかったため検証できずだった。
中干しの技術は天敵の観点から無しの方が有効である可能性が高い事がわかったので、来年の栽培の課題は中干し無し栽培に耐えうる減肥に絞る事ができた。
これはちょっとした案だけれども、

冬から春にかけてのレンゲ栽培で、初春の再び生育が旺盛になり始める頃に

米ぬかで追肥することが後の稲作で良い影響を与えるのでは?と予想している。

次作の課題である減肥のさじ加減の話だけれども、心配事として初期生育のリン酸の量が減る事がある。
微量要素は川の水の入水で補えるとして、リン酸の供給源の心当たりがない。
稲作は肥料成分ギリギリの施肥設計になっているので、供給源の候補がない成分は注意しておいた方が良い。
この問題はレンゲ栽培時の追肥に注目すれば回避出来る。
後は、レンゲ栽培時の米ぬか追肥分を加味して、稲作の方で一発肥料をどれだけ減肥するか?だ。
補足
リン酸問題のもうひとつの案として、廃菌床による土作りがある。
関連記事
ピンク色のキリギリスを見つけたよ

大阪府高槻市にある摂津峡公園に子供らと虫採りに行ったら、長男がピンクのキリギリス?を捕まえた。
ここで気になったのが、この昆虫のピンク色の色素は何だ?ということ。
とりあえず、今まで知り得た内容を整理することにしよう。
キリギリスの色は緑色と褐色がある。
バッタの基本的な色は緑色で、緑色は葉緑体の代謝産物に因るものであるはず。
褐色の方は、環境ストレスを感じた時に合成されるメラニンという色素で基礎の緑色を上塗りするように合成する。
これらの話を踏まえた上で、冒頭のピンク色のキリギリスの話題に戻す。
バッタ目の昆虫の近隣にいる目でカマキリ目があり、カマキリ目にはピンク色で有名なハナカマキリがいる。
ハナカマキリのピンク色の色素は何?の記事で、
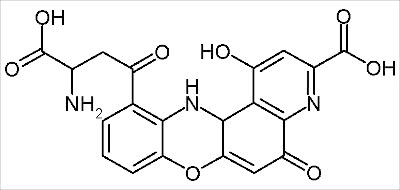
akane700 - 投稿者自身による作品, CC 表示-継承 3.0, リンクによる画像を改変
ハナカマキリのピンク色は還元型のキサントマチンという色素であった。

ピンクのキリギリスも同様の色素であるとして話を進めると、緑色の色素の下地にキサントマチンがあり、キサントマチンの発現量が多く、緑色の色素の量が少なく、環境ストレスも少ない状態であれば、ピンクのキリギリスが誕生することになる。
珍しい条件が二つあるので、再び見つけるのは難しそうだ。
関連記事
高槻の摂津峡で見かけた珍しいシダ
大阪府高槻市の摂津峡は街から近いにも関わらず、地形や植物を学ぶ上での教材がたくさんある。
羽片を意識すれば、シダ植物も全然違って見えてくるまでの記事で、シダに興味を持った際に摂津峡に行ってみたら、たくさんのシダがあって、1時間程歩くだけれでも、相当の目利きの練習ができた。
そんな中、


シダか迷う形状の葉があった。

矢印で示した箇所に特徴的な形質がある。
矢印の箇所までで軸の付け根の裂片の発生の向き(右か左か?)がかわる。
この形質を頼りにして山と渓谷社から出版されている桶川 修著 大作 晃一著 くらべてわかるシダを開いてみたら、チャセンシダ科のオクタマシダが該当した。
オクタマシダのオクタマは埼玉県の奥多摩のことだろうから、大阪で見れるものなのか?と気になって、検索をしてみたら、オクタマシダ|京都府レッドデータブック2015のページが引っかかった。
近畿レッドデータブックカテゴリーで絶滅危惧種C?
文中にアオガネシダに似ていると記載されていたので、アオガネシダの方を検索してみたら、アオガネシダ|京都府レッドデータブック2015のページが引っかかった。
アオガネシダは絶滅寸前種?
選定理由を読んでみると、
/***************************************************/
大阪府高槻市側からは、アオガネシダの立派な標本が残されている
/***************************************************/
と記載されているので、摂津峡でアオガネシダを見かけた事に関してはおかしくはない。
何はともあれ、摂津峡は私の自然観察眼を鍛えてくれることは間違いない。
2021年6月21日追記
今回の写真をみた方からチャセンシダのコバノヒノキシダでは?という連絡を頂きました。
連絡があって、コバノヒノキシダを調べてみたけれども、どっちも正しいように見えて、やはりシダ植物の見分けは難しい…
土作りを意識したレンゲ米栽培の田の田起こし
昨年、周辺の田がウンカの被害で収量が激減している中、無農薬で最後まで収量が減らなかった田を管理している方から、田起こししたという連絡があったので早速行ってみた。

連絡があった方はレンゲ米栽培をされている方で、レンゲが咲き乱れている中急いで耕起したそうだ。
この田で昨年と異なることは、
・レンゲの種まき前に土壌改良材のベントナイトや黒糖肥料を施肥した
・レンゲの鋤込み時期を前倒しした
※できれば、開花前に鋤き込めれば良かったが、諸事情により出来なかったらしい。
前者の方は有機物の増加と土壌への定着を目的とし、後者の方は亜鉛を含む微量要素の欠乏を避ける為に行う。
開花させることが前提のレンゲを栽培する時に注意すべきこと再び
これら二つの目的が組み合わさる事によって、病気や虫の食害を減らす事に繋がる。
前置きはここまでにしておいて、田起こし後の様子を見てみる。
田起こし中に雨が降ったそうで、少々こねてしまったようだけれども、


降雨中の耕起を加味しても、細かい土の塊が形成され、管理しやすそうな土表面となっていた。
今年はレンゲの背丈が例年よりも高くなっていたらしいので、土壌に投入された有機物量は多いはず。
地下部の根の発根状況はわからないが、それを踏まえても有機物量は増えたはずで、これらの有機物が土に馴染むという観点からも、レンゲの鋤込み時期をはやめた事は吉となると予想している。

昨年同様、管理コストが少なく、収量が少ない稲作を行えるだろうか?
今年も引き続き、田の様子を観測してみることにする。
関連記事
初春の緑地の林縁の木々たち

大阪府高槻市にある芥川緑地の端。
ここの写真は以前も何度か話題に挙げた事がある。

冬の写真とか。
この場所は注目していて、ブナ科の落葉樹(おそらくアベマキ)と常緑樹(おそらくアラカシ)の棲み分けが一目瞭然で、森林を学ぶ上で良質な教材になると思っている。
冬の写真と比べることで、アラカシを囲うようにアベマキが展開していて、光の競合でアラカシが負けているように見えるが、実は負けておらず棲み分けをしている事がよくわかる。
耐陰性が弱いアベマキは根元にドングリを落としても、耐陰性が強いアラカシに負けてしまうはずで、アベマキは林の外側(写真手前側)に向かって生育域を広げなければならない事が容易に想像出来る。
話は個々の木に移す。
これらの木を比較しながら見ることで他にも学んだ事がある。

おそらくアベマキであろう落葉樹の木をよく見ると、

当たり前だけれども、新しい葉が展開していた。
色が薄くてきれいな葉だ。
一方、常緑樹のカシの方を見てみると、



こちらも春の陽気に合わせて新しい葉を展開していた。
注目すべきは昨年の葉を覆うように新しい葉が展開していること。
常緑樹の葉にも寿命というものがあるので、新しい葉が出るのは当たり前の話だけれども、落葉樹と同じようなタイミングで新しい葉を出すのは観察していないと分からない事。
これらの内容から、ブナ科の落葉樹は春の陽気で新しい葉を展開する事を先に獲得して、その後に温度をシビアに感知して落葉する性質を獲得したのだなと想像が膨らむ。
落葉性という代謝の効率を高めて、成長を速くしたとしても、生存競争で必ずしも優位にはならない例として学ぶことは多いなと。
代謝の効率を高めると、森林の外側に生存の領域を広げる事が出来るが、森林の内側に戻ることはできない。
今回に似た内容でもっとダイナミックな棲み分けは高槻の隣の島本町にある若山神社で見ることが出来る。
関連記事

